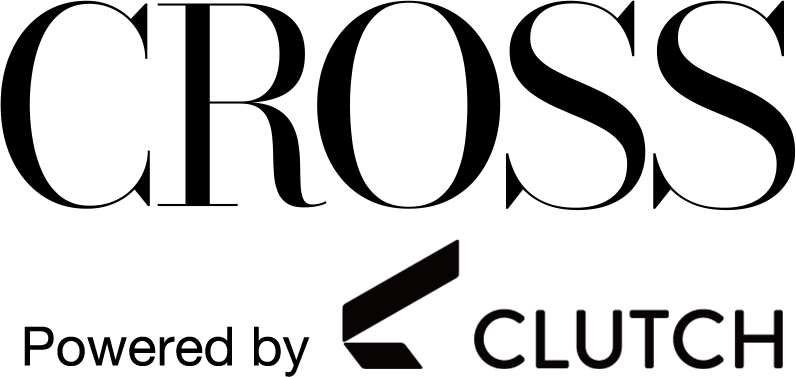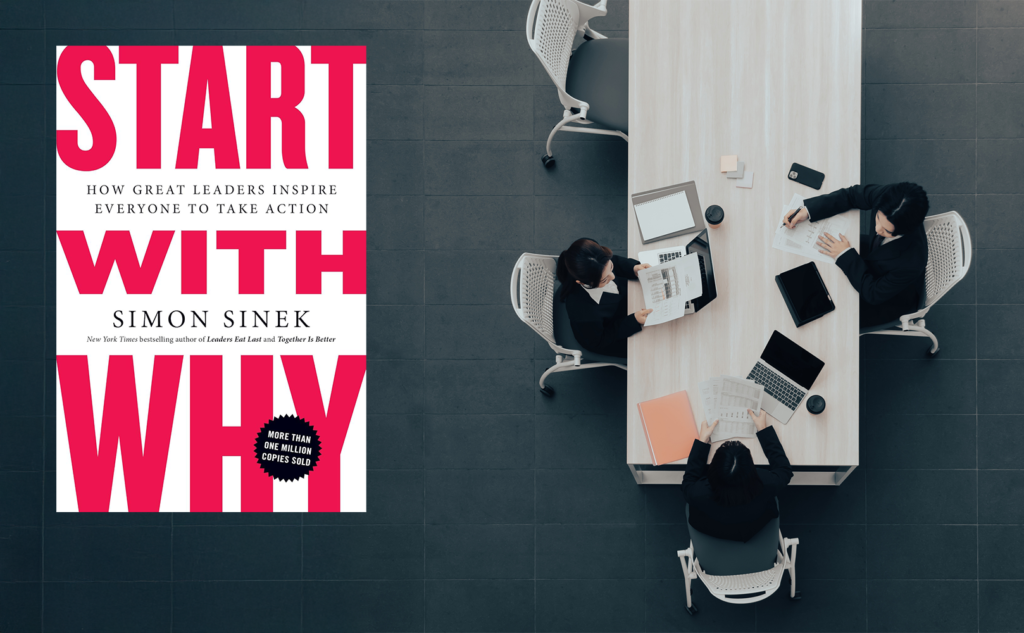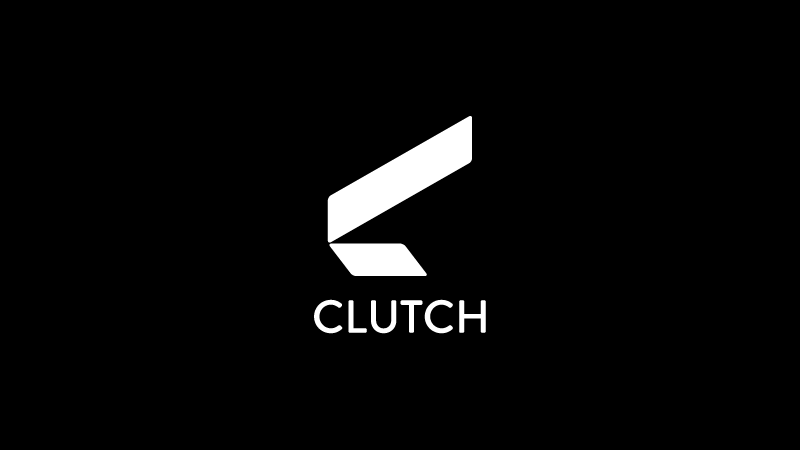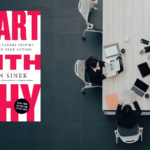はじめに
成功するブランドと他の企業の違いは何だろう?
どうすれば顧客に選ばれ続け、売上を安定的に伸ばしていけるのか?
多くのマーケターがこの課題に直面しているようです。
サイモン・シネックの「ゴールデンサークル理論」は、この課題に対する一つの視点を提供してくれると考えられます。
Web広告代理店の現場では、クライアントの売上向上が最終目標となることが多いでしょう。
機能や特徴だけを訴求するWeb広告は、効果が限定的な場合も少なくありません。
競合との差別化が難しくなっている今、ゴールデンサークル理論を活用することで、広告パフォーマンスの改善につながる可能性は十分にあるのではないでしょうか。
この考え方について、一緒に見ていきましょう。

ゴールデンサークル理論とは
サイモン・シネックのゴールデンサークル理論は、彼の著書「Start With Why(邦題:優れた人と組織はなぜそこから始めるのか)」で提唱された概念で、TEDトークでも紹介されています。
この理論では、組織やリーダーが人々に影響を与え、行動を促すための一つのアプローチが示されています。
ゴールデンサークルは3つの同心円で構成されているとされます:
- WHY(なぜ):中心の円。商品やサービスが顧客にもたらす価値、解決する課題、提供するベネフィットを表します。
- HOW(どのように):中間の円。そのベネフィットを実現するための差別化された方法やプロセス、アプローチを示します。
- WHAT(何を):外側の円。具体的な製品やサービスの機能や特徴を表します。
シネックの考えでは、多くの企業やマーケターはWHAT(製品・サービスの機能)から始め、次にHOW(差別化ポイント)を説明し、WHY(顧客価値やベネフィット)にはあまり触れない傾向があるようです。
一方で、影響力のあるマーケティングは、この順序を逆転させ、「WHY」、つまり顧客にとっての価値から始めることで共感を得やすくなると彼は主張しています。

人間の脳とゴールデンサークルの関係
シネックの理論が注目される理由の一つとして、人間の脳の構造との関連性が指摘されています。
彼の説明によれば、人間の脳は大きく分けて3つの部分に区分されるといいます:
- 新皮質(理性脳):理論的思考や言語処理を担当するとされる部分
- 辺縁系(感情脳):感情や意思決定、行動に関与するとされる部分
- 脳幹(爬虫類脳):本能的な反応を制御するとされる部分
シネックの主張によると、ゴールデンサークルの「WHY」のメッセージは人間の辺縁系(感情を司る部分)に働きかける傾向があり、感情的なつながりと信頼を生み出す効果が期待できるようです。
「WHY」から始めるコミュニケーションは、理性的な判断よりも感情的な共感を引き出し、行動喚起につながるケースが見られるという点は、広告制作において参考になる視点ではないでしょうか。

Web広告代理店としてのゴールデンサークル活用法
Web広告の施策を考える際、ゴールデンサークル理論を取り入れることで、広告パフォーマンスに好影響を与える可能性があります。
以下に、実際の業務で応用できそうな方法をいくつか紹介します。
1. ブランドストーリーの再構築
従来のアプローチの例:
「当社は最高品質のXを提供しています。最新技術Yを使用し、業界最高の機能Zを備えています。今すぐ購入しませんか?」
ゴールデンサークルアプローチの例:
「時間とコストの削減を求めるお客様のために(WHY)、AI分析技術で業務プロセスを最適化し(HOW)、クラウド型業務管理システムXを提供しています(WHAT)。」
このように、顧客の利益や課題解決を「WHY」として訴求することは、広告の反応率向上につながる傾向が見られます。
広告文やランディングページ制作では、「お客様が得られる価値」から書き始めるという方法も有効な選択肢となるでしょう。
2. ペルソナ設計の再考
従来のペルソナ設計は人口統計学的データや行動パターンに重点を置くことが一般的ですが、ゴールデンサークル理論の視点を取り入れたペルソナ設計では、ターゲットオーディエンスの「WHY」—彼らの価値観や動機—にも焦点を当てることで新たな洞察が得られる場合があります。
広告運用において、以下のような視点を加えることで、オーディエンス理解を深める一助となるでしょう:
- このオーディエンスが重視している価値は何か?
- 彼らの購買行動を動機づけている要因は何か?
- どのような課題解決や目標達成に関心を持っているか?
これらの視点を踏まえ、クライアントの提供価値とオーディエンスの求める価値が合致するようなメッセージを検討するというアプローチは、特に競合の多い市場において差別化要因となる可能性を秘めています。
3. コンテンツマーケティング戦略への応用
ゴールデンサークル理論の視点は、コンテンツマーケティング戦略の立案にも役立つ側面があります:
WHYに関連するコンテンツ:顧客価値や課題解決を伝えるコンテンツ(お客様の声、利用によるメリット、課題解決事例など)
HOWに関連するコンテンツ:ブランドのアプローチやプロセスを示すコンテンツ(ケーススタディ、サービス提供方法、差別化ポイントを示す比較情報など)
WHATに関連するコンテンツ:製品やサービスの具体的な特徴や機能を説明するコンテンツ(製品紹介、使用方法、スペック情報など)
Web広告運用においては、これらの異なるタイプのコンテンツをカスタマージャーニーの各段階に合わせて配置することで、顧客の意思決定プロセスに沿ったアプローチが可能になると考えられます。
特にリターゲティング広告では、WHYからHOW、WHATへの流れに沿ったメッセージング設計が効果的なケースも多いようです。
4. 広告クリエイティブとメッセージングの再構築
ゴールデンサークル理論をディスプレイ広告、動画広告、ソーシャルメディア広告などのクリエイティブ制作にも適用できます:
- 広告見出し:製品の特徴ではなく、ブランドの信念や目的(WHY)を前面に出す
- 広告ビジュアル:製品だけでなく、ブランドの存在意義や価値観を視覚的に表現する
- CTA(行動喚起):単なる「今すぐ購入」ではなく、ブランドの使命に参加するよう促す
例えば、「最新のフィットネスアプリを今すぐダウンロード」というCTAよりも、「より健康な世界を共に創造しよう」というメッセージの方が、共感と行動を生み出す可能性が高くなります。
5. SEO・SEM戦略の拡張
検索エンジン最適化(SEO)と検索エンジンマーケティング(SEM)の戦略にもゴールデンサークル理論を取り入れることができます:
- キーワードリサーチ:製品機能に関するキーワードだけでなく、ブランドの価値観や目的に関連するキーワードも含める
- 広告コピー:Google広告やMicrosoft広告のコピーにブランドの「WHY」を組み込む
- ランディングページ:検索から訪れるユーザーに対して、まずブランドの存在意義を伝え、その後に製品情報を提供する構成にする
Web広告代理店として、クライアントのSEO/SEM戦略をWHYからWHAT(検索意図)へと段階的に導くアプローチを提案できます。

検討できる実践方法
実際の広告運用業務でゴールデンサークル理論の視点を取り入れる場合、以下のようなステップが参考になるかもしれません。
1. 顧客視点の「WHY」の検討
クライアントとの打ち合わせでは、以下のような質問を通じて訴求ポイントを検討することができるでしょう:
- お客様はこの製品・サービスでどのような課題の解決を期待しているでしょうか?
- お客様にとって、時間やコストの面でどのようなメリットがあるでしょうか?
- 競合他社と比較して、どのような価値を提供できる可能性がありますか?
- お客様のビジネスや生活にどのように貢献できる可能性がありますか?
2. メッセージングフレームワークの検討
検討した価値提案を中心に、HOW、WHATを組み込んだメッセージングの構成を考えてみることもできるでしょう:
- WHYに関する要素:顧客にとっての価値や解決される課題
- HOWに関する要素:価値を提供するための差別化されたアプローチ
- WHATに関する要素:提供する具体的な製品やサービスの特徴
3. デジタルタッチポイントでの適用検討
クライアントの既存のデジタルタッチポイントを分析し、新しい視点でのアプローチを検討することもできるでしょう:
- ウェブサイト:価値提案を伝えるコンテンツと、具体的な製品・サービス情報のバランス
- ソーシャルメディア:顧客価値に関連するメッセージの取り入れ方
- 広告キャンペーン:顧客視点の価値を取り入れた広告クリエイティブとコピーの検討
- メールマーケティング:顧客にとっての価値を意識した顧客コミュニケーション
4. 効果測定の視点
このアプローチを試す場合、以下のような指標で効果を観察すると良いでしょう:
- 直接的効果指標:広告クリック率(CTR)、コンバージョン率、獲得単価(CPA)の変化
- 間接的効果指標:直帰率、滞在時間、リピート率などの変化
- 長期的効果指標:顧客生涯価値(LTV)、リファラル(紹介)の傾向
「WHY」を意識した訴求方法を取り入れた広告が、従来の機能訴求型広告と比較してどのような違いをもたらすかは、業界や商材、ターゲット層によって結果が異なる点に留意する必要があります。
A/Bテストなどを通じて、自社の状況に合った最適なアプローチを見つけていくという姿勢が望ましいといえるでしょう。

まとめ:検討してみたい実践のヒント
ゴールデンサークル理論は、Web広告アプローチを考える上での一つの視点として参考になるかもしれません。この考え方を取り入れる場合、「顧客にとっての価値(WHY)」を意識することが一つのポイントになるでしょう。
広告運用の参考として:
- 広告文に「お客様が得られる可能性のあるメリット」を含める
- 可能であれば、具体的な価値を示す(例:作業時間短縮、コスト効率化など)
- 差別化ポイント(HOW)を適切に伝える
- 製品説明(WHAT)とのバランスを考慮する
このようなアプローチで広告を組み立てることで、広告パフォーマンスに良い影響をもたらす可能性があります。
特に競争が激しい業界や、商品の差別化が難しい分野では、新しい切り口として検討する価値があるかもしれません。
「この商品は何ができるか」だけでなく「この商品であなたはどのような課題を解決できるか」という視点を取り入れることで、広告の訴求力を高める一助になる可能性があります。